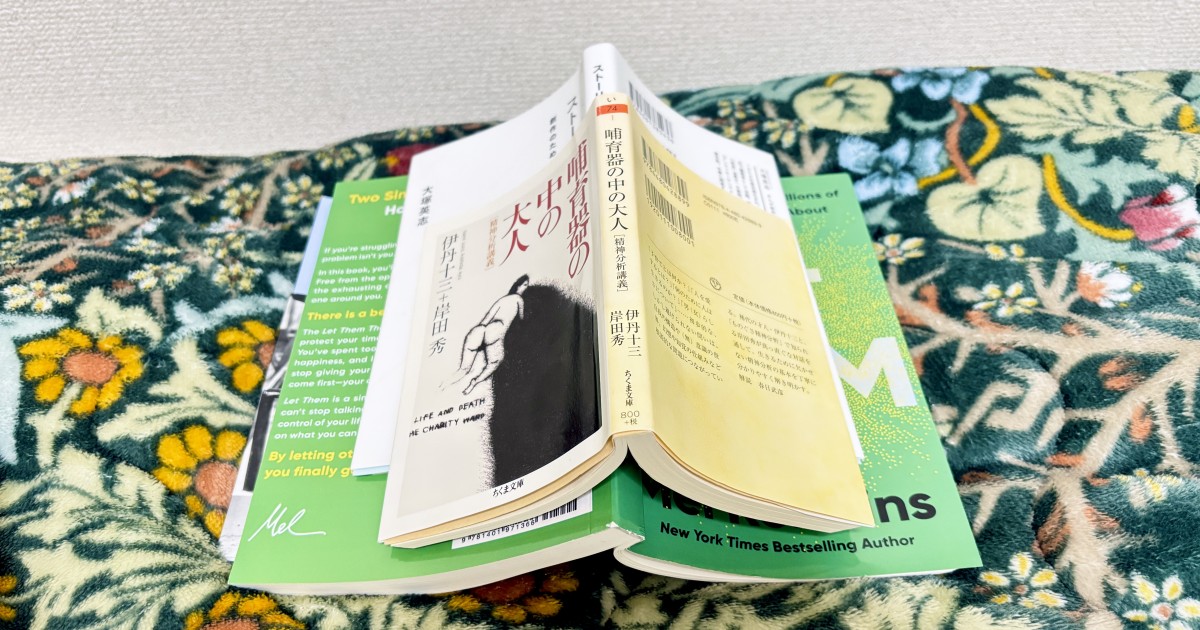《花恋04》『花束みたいな恋をした』のジェンダー観とフェミニズム
さて。
同棲譚とジェンダー・フェミニズムは70年代より切り離せないものでありまして、上村一夫『同棲時代』を読むとその時代において男がどうで女がどうだったというのがとても見えてくる、嫌なくらいに見えてきます(それでも上村先生は今日子を言いたいこと言う先鋭的な女として描きあげたわけですが)。
その点について『花束みたいな恋をした』はどうだったのかを、思いついた順からだだーっと書いていきます。
・台所まわりについては性的役割分担を強化しない描写をしている
この映画は台所での様子がそれほど克明には出てこないのですが、観測できる範囲では絹よりは麦のほうが積極的に台所に立っているようです。
絹を初めて家に招き入れた時に麦は焼きおにぎりを作っています。ガスコンロにちゃんと網をのせて。あの感じは平松洋子さんのエッセイとか絶対読んでる。
そのほかにも、湯気がもうもうと立ち上るナポリタンやそうめんを出しています。
二人暮らしを始めるようになってからは、絹の両親が来た時には豪華な惣菜がテーブルに並んでいたけどあれは両親が買ってきたものなのかもしれません。
麦の帰宅が20時をすぎることもあるなどの説明はあっても、その時の食事の支度をどうするか(たとえば「夕食先に食べちゃっていい?」とか「遅くなるなら作らないから連絡して」とか)といったことに関しては描かれていないし、問題になっているような様子も私は感じ取れませんでした。
麦がコンビニで買ってきたようなうどんを食べているシーンがあったので、食事はそれぞれで用意していたのかも。
別れたあとの3ヶ月の間に、丁寧に作られたハンバーグが食卓に並んでいたけれど、あれはどちらが作ったのか。少なくとも絹が腕をふるって「さあ召し上がれ」といった感じではありませんでした。
そんな感じで、「俺のメシは?」とか「具合悪いなら寝てていいよ俺は食って帰るから」とか言うような価値観は持っていないことはわかるものの、ことさらにザ・家事面で自立した男子を描いているような気負いもなく、ここにも想像の余地がちょうどよく残されているように思いました。
・DVについてのシーンは特に意図的に「余地」を残した描写をしている
アート系の友人たちとの食事をしている時(たしか麦はいなかった)、菜那(カメラマンの海人と付き合っていた子)が別れた理由を聞かれて、髪を持ち上げ額の傷を見せる。
「殴ったの?あいつ最低…」といった女子のリアクションのあと、すかさず男子が「でもあいつも辛かったんだと思いますよ、仕事がうまくいかなくて…」的な謎フォローを入れる。「こいつ何言ってんだ?」というドン引きの視線を送る女子。
私は個人的に、映画全体の中でもこのシーンが一番、鑑賞者に感想を委ねているところだと思いました。
だって「あいつも辛かったんだと思いますよ」のあとに「いやそういう話じゃないでしょ、DVだよこれ」とツッコミを入れさせるほうが、作り手としてはすっきりするし楽なんです。変に物議を醸す心配もないし。でもあえて、そのツッコミを挟まなかった。
それは脚本家が「あいつも辛かった」って言っちゃう側の人間でその見方をゴリ押ししたいから…ではないですよ、当然。
もしそうなら、海人の辛さはもっと共感を呼ぶものとして描かれていたことでしょうし、言っちゃった友人に送られるドン引きの視線が描かれていることからも、海人擁護側に立っているわけではないことはわかります。
ではなぜツッコミを挟まなかったのか?
それは、鑑賞者がどちらの見方に立つのかをあえて委ねる、ということをしたかったからなのだと思います。
とはいえ、そのDVに対する判断材料はそこだけではありません。そこに至るまでに、海人が菜那を銀座の「オヤジを転がす」店で働かせていて、麦にもその選択肢(絹に「女」を使って稼がせる)を勧めるという描写があります。
海人はそういう人間であるということを踏まえていれば、そのあとの菜那によるDV被害告白は信じるに値する。(海人が殴るシーンは描かれていないので、もし前述のシーンがなければ「これは菜那の狂言だ」と思う人もいたかもしれません)
自己中心的で、女性を搾取する性格であると示されている海人が菜那を殴った。まず鑑賞者が、このシンプルな情報を事実として認識できるかどうか。
そしてそのあと続く、友人による海人の擁護をどう捉えるか。
与えられた情報と、これまで培ってきた経験や倫理観を使って、鑑賞者ひとりひとりがこのことについて考えること。語り合うこと。その余地が、ここにはしっかりと意図的に残されているのです。
明確にDVを否定・批判する形になっていないことで「これはフェミニズムのほうに立っていない」と感じる人もいるかもしれませんが、私はそうは思いません。こういった問題提起の方法もあるのだなと感じ入った次第です。
・親世代の価値観がステレオタイプではない
絹の両親は広告代理店で共働き。そのルックスや話しぶりから、どちらも最前線でバリバリ働いてきた人たちであることを思わせます。
特徴的なのは、社会の一員として(就職して)働くことの意義や責任について娘の恋人に語るのは父親ではなく母親であること。
そして働くことを勧めはするものの、籍を入れてちゃんとして娘を養えとか子供を作って普通の家庭を作れといったような家族観をゴリ押ししてきたりはしないこと。
大きな会社じゃなくてもいいから社会の一員として働きなさい、というメッセージは、家父長制にとらわれた親というよりも、社会という枠組み至上主義の人たちという感じがしました。
しかしそれはそれで脅威であるし、家父長制との親和性もある考えであると私は思います。
事実その後の麦はそこにとらわれていきますし、さらに絹に「俺が稼ぐからずっと家にいればいい」と言ってしまうところまで達してしまいます。
麦の親に関しては父親しか出てきませんでしたが、その父親も独特でした。
「長岡の人間なら花火のことだけ考えろ」という、これはこれでなんだろう、地元至上主義?しかしそれも、社会という枠組み至上主義と同様に、家父長制との親和性が高いものであると思います。
とはいえ、やはり今まで恋愛ものでステレオタイプとして描かれてきた「結婚を迫る親」「男は仕事、女は家庭を勧める親」とはちょっと違うキャラクターであったし、それをどのようにとらえるかもやはり鑑賞者に委ねられているのではないでしょうか。
・「女が結婚を迫り男がはぐらかす」従来の物語からの脱却
この点はとてもわかりやすく描かれており、結婚について話すのはいつも麦からです。
絹も「今のってプロポーズ?思ってたのと違った」と言っていたことから、結婚をしたくないというわけではなく、むしろプロポーズというものに少し夢と期待を持つ程度には結婚願望があったのではないでしょうか。
しかしそれを待ち望んだり、結婚に話が進んでいくようにまわりから固めていったりするような描写はありません。
そういったところから、作り手側は「女性は結婚をしたがるもの」「女性は子供を欲しがるもの」という思い込みを排除した上で、「絹」というひとりの人間を描いているのだと私は感じました。
麦においても、結婚を口にしてしまう理由というものがその都度示唆されており、決して「男は女を養うもの」とか「男は結婚して一人前」とか「男は仕事、女は家庭」とかゴリッゴリに思っている男ではないということもわかるように、作られていると思います。
「男と女」を描いているようでいて「麦と絹」を描いている…というと綺麗すぎに聞こえるかもしれませんが、今まで枷のようにはめられてきたよくある男女の設定(私もよく使ってます)から脱却していることこそが、この映画がジェンダーについてしっかりと考えて作られている証左ではないでしょうか。
・委ねられている私たちはどう観るか
委ねられているのだから、どう観るのかはもちろん自由であり、そこにだれかが正解や不正解を突きつける必要も権利もありません。
しかし、「麦が社会人として弱すぎた。あれでは結婚できたとしてもやっていけなかっただろう」「麦が男として社会に身を捧げているのだから、絹が麦をもっとサポートすべきだった」…そういった感想(私が実際見聞きしたものです)はもしかしたら、自身のジェンダー観と大きく結びついているのではないか。私はそんなふうに提起したいと思います。
推敲なしの書きっ放しですが、ひとまずここで終わります。
すでに登録済みの方は こちら